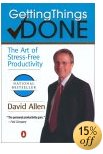見える化とは (5) 「見える化」の10のポイント
 前回に続いて、「見える化」本のご紹介です。
前回に続いて、「見える化」本のご紹介です。
書籍の最後で、効果的な「見える化」のための10のポイントが掲載されていますので、最後にまとめとして紹介したいと思います。(このポイントは以前にZDNetの記事に掲載されていたものと同じです。)
■効果的な「見える化」のための10のポイント
1 まず現状の棚卸しから始める
2 「見せたくないもの」「見せられないもの」ほど「見える化」する
3 「見える」もの、「見せる」ものを絞り込む
4 態度・タイミングを重視する
5 アナログとデジタルを使い分ける
6 わかりやすく、シンプルに
7 現場の当事者自身が「見える」ようにし、仕組みもつくる
8 本当の勝負は「見えたあと」
9 「見える化」のノウハウを共有する
10 経営トップが「見える化」を牽引する
個人的に印象に残っているのは、やはり5番のアナログとデジタルの使い分けでしょうか。
手段が目的化しないように、まず最初の定義が非常に重要だと感じます。
また「見せたくないもの」「見せられないもの」ほど見える化するというのも重要ですね。
特にシステムを構築する際には、見せやすいものを見られるシステムになってしまったり、実際に必要な情報を表示するのに異様に面倒なシステムになってしまったりしがちですので注意したいところです。
詳細については、是非書籍を読むことをお勧めします。
【関連記事】
・見える化とは (1) 現場力を向上する
・見える化とは (2) 「見る」ではなく「見える」
・見える化とは (3) 「見える化」の5つのカテゴリー
・見える化とは (4) 「見える化」すべき3つの情報
・見える化とは (5) 「見える化」の10のポイント
 | 見える化-強い企業をつくる「見える」仕組み 遠藤 功 Amazonで詳しく見る by G-Tools |